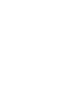News&Topics
HOME > News&Topics > 秋の節句とは?
2025-09-09
秋の節句とは?

みなさんは「重陽の節句(ちょうようのせっく)」をご存じでしょうか。
9月9日がその日にあたります。
節句と聞くと、5月5日の端午の節句や、7月7日の七夕を思い浮かべる方が多いかもしれませんね。実は江戸幕府が決めた「五節句」には、これらに加えて、1月7日の人日の節句、3月3日の上巳の節句、そして9月9日の重陽の節句があります。
人日の節句には七草粥を食べ、上巳の節句にはひな祭りを祝うように、五節句そのものはなくなった今でも、多くの行事は生活の中に残っています。けれども、重陽の節句だけは忘れられがちです。なぜなのでしょうか。
理由のひとつは、旧暦と新暦のずれです。本来は菊の花が盛りを迎える時期なのに、新暦ではちょうどそのタイミングと合わなくなってしまったのです。ただ、桃の節句や端午の節句も同じように季節がずれているので、それだけが理由とは言えません。
大きな違いは、桃の節句や端午の節句が「子どもの成長を願う」家庭に直結した行事として残ったのに対して、重陽の節句は「菊を眺めて長寿を願う」という、少し上品で抽象的な行事だったことです。そのため庶民の生活にはなじみにくく、明治以降の祝日整理の中で自然とすたれていったと考えられています。
そもそも「節句」は、もとは「節供」と書き、季節のごちそうを意味しました。旬の食材を神様にお供えし、みんなでいただくことで健康を祈る日だったのです。旬のものは栄養たっぷりで、いちばんおいしい時期とされています。
まだまだ暑さは残りますが、これから訪れる秋の味覚を楽しみに待ちたいですね。
9月9日がその日にあたります。
節句と聞くと、5月5日の端午の節句や、7月7日の七夕を思い浮かべる方が多いかもしれませんね。実は江戸幕府が決めた「五節句」には、これらに加えて、1月7日の人日の節句、3月3日の上巳の節句、そして9月9日の重陽の節句があります。
人日の節句には七草粥を食べ、上巳の節句にはひな祭りを祝うように、五節句そのものはなくなった今でも、多くの行事は生活の中に残っています。けれども、重陽の節句だけは忘れられがちです。なぜなのでしょうか。
理由のひとつは、旧暦と新暦のずれです。本来は菊の花が盛りを迎える時期なのに、新暦ではちょうどそのタイミングと合わなくなってしまったのです。ただ、桃の節句や端午の節句も同じように季節がずれているので、それだけが理由とは言えません。
大きな違いは、桃の節句や端午の節句が「子どもの成長を願う」家庭に直結した行事として残ったのに対して、重陽の節句は「菊を眺めて長寿を願う」という、少し上品で抽象的な行事だったことです。そのため庶民の生活にはなじみにくく、明治以降の祝日整理の中で自然とすたれていったと考えられています。
そもそも「節句」は、もとは「節供」と書き、季節のごちそうを意味しました。旬の食材を神様にお供えし、みんなでいただくことで健康を祈る日だったのです。旬のものは栄養たっぷりで、いちばんおいしい時期とされています。
まだまだ暑さは残りますが、これから訪れる秋の味覚を楽しみに待ちたいですね。